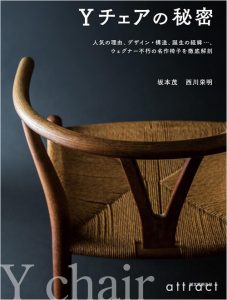「Yチェア」と呼ばれるデンマーク製の著名な椅子がある。日本で最も売れている北欧家具である。その椅子にまつわる書籍「Yチェアの秘密」の著者である坂本茂氏(木工デザイナー)と西川栄明氏(木工関連書ライター)の講演会に参加して来た。この書籍が出版されてから全国各地で幾度か開催されているのだが、先週京都工繊大での学生向け講演に学外からも参加可能という事で、滋賀から琵琶湖大橋を渡り大原を通り抜けて同大学キャンパスへ行ってきたのである。
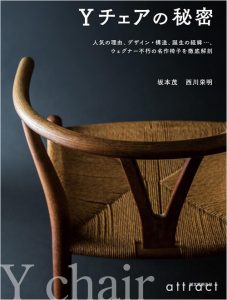
デンマークの巨匠ハンスJ.ウェグナーがデザインしたこのYチェア、発売から65年以上経つのにこの間延々と世界中で売れ続け、日本だけで今でも年間5~6千脚売れているのだとか。毎日20脚という凄まじさ。生涯何百脚もの名作椅子を残したウェグナーの作品の中の金字塔であり、その秘密が解き明かされるという訳である。

この椅子を日本で輸入販売している会社で長年この椅子に関わって来られたという坂本氏の解説、表も裏も知り尽くす人ならではの解説に聞き耳を立てた。
数多くの家具の中で椅子ほど難しくて面白いものはない、と思う。デザインが優れていて美しいこと、座り心地のいいこと、そこそこ軽量で移動や持ち運び可能であることに加えて、何といっても毎日その上で何時間も腰かけて体重を掛けられ続けることに耐える頑丈さ、毎日使って飽きの来ないこと、食卓椅子など同時に複数脚を揃えることから価格的な制約も大きい、などなど。機能と美と耐久性などすべてを高次元で実現しない限り、椅子としての期待に応えられない、のである。
ということを自覚するあまり、未だに自分の椅子へのチャレンジが出来ないでいる(子供椅子とスツールぐらいに留まってる)。世の中にあまた存在する市販椅子にとって代わるようなオリジナル椅子のアイディアも未だ湧いてこない。
そんな言い訳を頭の片隅に浮かべている間に講演は先へと進み、やがて第二部の座編み実演が始まった。この椅子の座面は板張りでも革や布地張りでもない特殊な紙ヒモで編みこまれているのである。茶色い紙を直径4mmほどのロープ上に巻いたペーパーコードと呼ばれるヒモを縦横に巡らせて座面となすのである。一脚分におよそ120メートルものコードが使われる。
実演される坂本氏、このペーパーコード張りの達人で一脚編み上げるのに驚きの45分、日本一は無論もしや世界一では、とのこと。Yチェアの座面は、10年~20年と使い続けるとさすがにペーパーコードが伸び編み目も崩れ、座り心地が悪くなるので張替える必要が出てくるのだが、この張替えを請け負うために必要なペーパーコードをデンマークからコンテナ買いをする、などとサラリといって聴衆をどよめかせるのである。

というようなわけで、完成したYチェアがこちら。右側は前回張替えから20年経過したYチェア、左側が張替え直後の美しい座面。試しに腰掛けると座り心地も全く違う。ただ、背中のYの字の根元が深く腰掛けた際には尾てい骨あたりに触れるのが、個人的には正直なところ少し?と思ったりもした。

一方こちらは、工房の片隅に転がっているワタクシが以前ペーパーコードを張ったスツールの写真。だらしなくコードの間に隙間が空いていてヒモが交差するXの形もビミョーにカッコ悪い。編み上げた直後から、カッコ悪さを自覚していたのだが、今回講習でのヒントを参考にいよいよ張替えねば、である。

ということでクダクダ長文失礼しました。この機会を頂戴した西川様(この書籍にサインいただいた)、坂本様、有難うございました。大変勉強になりました。もっとも、このおふたりがこのブログを読まれる機会は、永久に来ないと思いますけどね。











 製作途中
製作途中 完成後
完成後





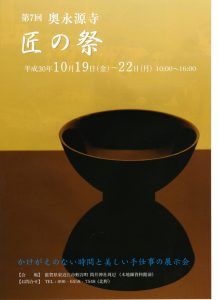
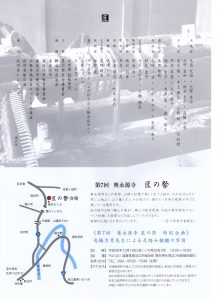
 残すは塗装のみ
残すは塗装のみ