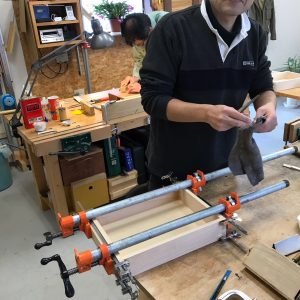年末に出来なかった自動鉋盤の整備が3月に入ってようやく完了した。刃の切れ味が落ちたので予備の刃と交換し、合わせてベアリングのオイルバスに入っている機械油の交換である。
材の送りは、未だ快調なので調整不要。刃を変えると材の逆目も起きずツヤツヤの仕上がりに復帰した。
で、刃の研ぎを依頼するための工房近くの一円機械さんに持って行ったのだが、図らずもスクラップ置き場に破断した帯鋸の刃が捨てられていた。以前参加した曲木講習会で曲木に必須の帯鉄は、帯鋸の刃から刃の部分を切り落としたハガネのベルトがベストというのを聞いていた。ということでその帯鋸のスクラップを喜んでもらって帰ったのは言うまでもない。
幅10cmほどの、何か所かでひん曲がった恐ろし気な鋸刃である。早速、工房のディスクグラインダーに金属切断用の刃を取り付けてこの鋸刃から3cm幅程度の鋼板を切り取ろうと悪戦苦闘の開始。
取りあえず、刃の折れ曲がった箇所で切断して、一番短い部分を使って3cm幅に切断してみた。ディスクサンダーをスタンドに取り付けた工具で何とか短い帯鉄を切り取ることは出来た。だが、欲しいのは大人用椅子に使う2m超と子供用椅子に使う1.2m程度の長さである。その長さを切り取る根性なく(余程うまくやらないと切断ディスクが折れて飛び散りそうで怖い)、この作戦はあえなく中止。
ここで止めるとまた何年かがあっという間に経過しそうなので、引き続きネット検索して帯鋸の製作会社を検索してみた。関西圏の会社にひとつ目星をつけて、電話して事情を話すと帯鋸刃を作る際の材料から刃のない帯鉄を譲ってもらえるとのこと。早速、幅と長さの連絡をしたところ、数日後にはついに待望のハガネの帯鉄がついに手に入ったのである。
これでやっと曲木に再チャレンジの道具立てが揃った。遠からず再挑戦である。因みに前回の失敗の原因のひとつは、梱包用の幅の狭い鉄ベルトを使ったので棒のサイズがベルトより広くてそこから割れが生じた、というのが勝手な仮説である。結局、まともな帯鉄入手まで3~4年も掛かったことになるのだが、今回のスクラップ帯鋸の発見を機に思いがけず解決したのであった。
今度、機械屋さんに行く際に不要となった帯鋸刃を再度スクラップ置き場に戻させてもらわねばならない。市のごみ回収にこんなのを出すと叱られそうだしね。