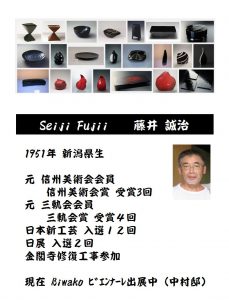高山からの帰り道、岐阜県各務原で月に一度開催されている木材市がちょうど開催されていて初挑戦して来た。 広い敷地いっぱいに原木やら巨大な一枚板やらが、所狭しと並べられていてこれらをたったの一日で競って売り切ってしまうらしい。残念ながら天気が悪く時々土砂降りになる中、傘を広げたり畳んだりしながらおよそ3時間の初チャレンジを楽しんだ。この木材市は誰でも参加できるようにオープン化し、日本でも有数の活況ある市らしい。 時代に合わせて変身できるところだけが生き残るというのは、世の常のようである。


受付で手付金を払って、番号札をもらい競りの人ごみの中へ乱入するも、ひとつの競りに掛かる時間は数十秒、長くてもせいぜい1分程度、とてもじゃないが百戦錬磨の参加者に太刀打ち出来そうにない。一瞬でも躊躇する間に競りは、終わってしまう。 どこぞの銘木屋のオヤジらしき太った男性が器用に値段を下げたり(買い手がいないと下がっていくのである)競ったりして次々と決めていくのを横目で見ながら買い方の勉強である。一緒に行ったカミさんが、ブレーキ役かと思いきやしきりにアクセルを踏むのでビックリ。というわけで空振りを数回繰り返した後に3m程の栗の板5枚セットを初落札。いつもお世話になっている材木屋さんの乾燥材と違って未乾燥で当分使えない。1~2年は寝かしておかねばならないので不自由極まりないがまあモノは試しである。
高級な一枚板は、屋内の会場に並べられている。この写真のように身長の2~3倍もありそうな巨大なモノもずらりと並んでいて見事な眺め。 家具屋で見る一枚板は、いわゆる目玉が飛び出る値付けだが、さすがに製材しただけの未乾燥の一枚板はそれより手ごろな値段ではあるのだが、乾燥してまっ平らに鉋掛けをする(鉋盤にも掛からないデカさなので手でやるしかない)までの手間は尋常ではなさげ。 根性のない私は機械に掛かる程度の控えめの幅のチェリー板を1枚だけ試しにゲット。午後からは原木の競り開始となるが、さすがにそこまでの根性はないので昼休み時間に精算を終えて帰途についた。

 買い子178番、チェリーお買い上げ(競い手なく)
買い子178番、チェリーお買い上げ(競い手なく)
今回乗用車で出掛けたので、来週改めて軽トラに乗って材を取りに行かねばならない。無事に載せられるのか?
はたまた、家具になる日は一体いつやって来るのやら、ではある。